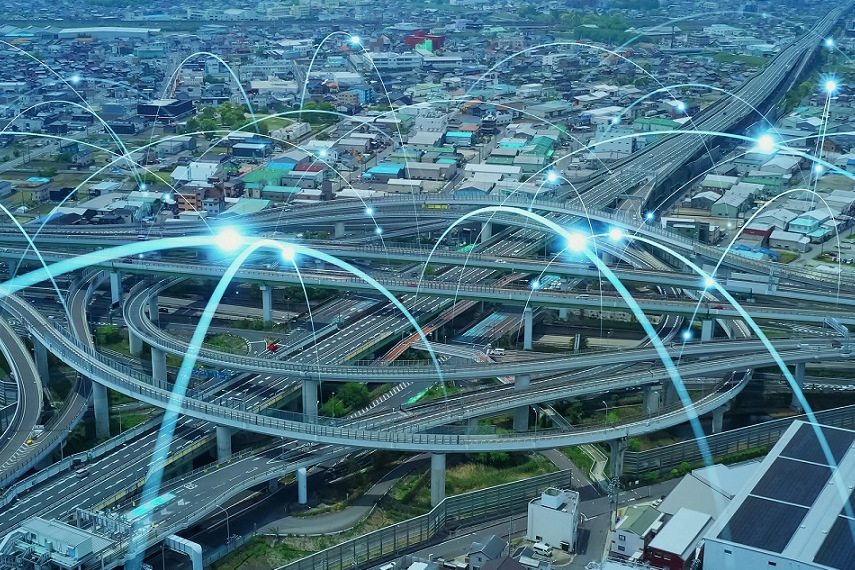交通システムをITで一括管理!移動の効率化を叶える「MaaS」とは

ITの目覚ましい発達にともない、さまざまな技術用語が生まれているのをご存知でしょうか。こうしたなか、「MaaS(マース)」という新しい取り組みが最近注目され始めています。
MaaSとは、英語の「Mobility as a Service(モビリティ・アズ・ア・サービス)」の頭文字を取った略称です。鉄道や航空機、バス、タクシー、レンタカー、カーシェアリングといった、自家用車以外の複数のモビリティサービス(交通手段)を利用する際、これまではそれぞれ個別に予約・決済を行っていましたが、ITの力を借りて一括予約・一括決済を可能にし、シームレスに利用できるようにする仕組みのことを指します。
MaaSに明確な定義があるわけではありませんが、国土交通省は次のように説明しています※1。
「地域住民や旅行者1人ひとりのトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスであり、観光や医療等の目的地における交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段となるもの」
つまり、MaaSの大きな目的は、社会インフラである交通システムをITによって効率化し、有効活用することです。
MaaS実現までの「5段階」
国土交通省などによれば、MaaSは、システム統合の度合いによって、次の5段階に分けられます※2。
■レベル0
システムがまだ統合されておらず、交通機関がそれぞれバラバラにサービスを提供している段階です。たとえば、鉄道や路線バスが時刻表を掲示したり、運行状況を掲示板で知らせたりしている状態を指します。
■レベル1
交通情報が統合され、複数の交通手段を1つのプラットフォームで比較し、ルート検索や運賃情報などが利用者に提供される段階です。「NAVITIME」や「Googleマップ」、「ジョルダン」といった路線検索サービスがその代表例として挙げられます。
■レベル2
路線検索や運賃の確認だけでなく、予約・決済までの手続きもワンストップで完了できる段階です。
■レベル3
複数の交通サービスが1つのプラットフォームで統合され、パッケージ化された段階です。代表例としては、国内でも一部実験的に始まっている「定額乗り放題」サービス(サブスクリプションサービス)が挙げられます。
■レベル4
もっとも高度化した「レベル4」は、交通機関と国や地方自治体が連携して、MaaSを活用して人流や物流の適正化を図ったり、都市計画や街づくりに組み込んだりする段階を指します。
JR西日本が開発したMaaSアプリ「WESTER」

交通機関ではMaaSを重要な経営課題と捕らえ、大手鉄道会社を中心にMaaSを推進しています。
JR西日本は2023年2月22日、観光型MaaS「setowa(現:tabiwa by WESTER)」に続き、MaaSアプリ「WESTER」をリリースしました※3。スマートフォンに「マイ駅登録」や「マイ区間登録」などをしておけば、間もなく到着する列車や周辺の列車走行位置などの情報に、すぐにアクセスできます。
全国の経路検索機能、ネット予約サービスとの連携によって、移動のプランニングや列車予約もワンタッチで可能に。最寄り駅や現在地周辺駅の平日・休日別の混雑度傾向も確認できるほか、イベント・スポット情報やそれに関連した経路検索もスムーズにできます。さらに、利用先の駅周辺で使えるクーポンも配信されるなど、機能が充実しています。
また、JR西日本は2023年3月からグループ共通の新たなポイントサービス「WESTERポイント」の新規会員受付をスタート。「J-WESTポイント」や「ICOCAポイント」といった、既存のグループのポイントサービスを統合するそうです。
「WESTERアプリ」には、ポイントカード機能が搭載されています。たとえば、グループのショッピングセンターやホテル、駅ナカ店鋪などで提示したり、ネット列車予約サービスを利用したりすると、料金の約1%分のポイントを獲得できるとのこと。貯めたポイントを1ポイント=1円相当として、店鋪やネットサービスで使ったり、商品に交換したりするほか、グループの交通系ICカード「ICOCA」へのポイントにもチャージできます。
つまり、WESTERは、交通手段や関連サービスを一体化させるMaaSの機能だけでなく、ポイント機能を拡充することによって、キャッシュレス決済の推進につながっているのです。
さらに、4月からはWESTERのアップデート版も提供されるようになりました。
アップデート版では、
1 WESTERポイントが貯まる・使える機能
2 予約履歴から再予約できる機能
3 WESTERのIDを作成してICOCAの番号を登録する機能
4 スタンプラリー実績の端末引継ぎ
という、4つの機能を追加したとのこと。ポイントが貯まる・使える機能には、WESTERポイントの付与・利用ができる会員証も表示できるようになるそうです。
なお、JR西日本は2023年3月、顔認証機能を使ったチケットレス・ウォークイン型の自動改札機を大阪駅に設置しました※4。これもMaaSの一環と位置づけられています。
「MaaS先進国」フィンランドの取り組み

既存の交通システムを変革するMaaSは国外でも注目度が高まっており、官民連携による実用化や実証実験が、すでに世界各国で進められています。とりわけ、欧州ではMaaSの導入が盛んで、なかでも北欧のフィンランドが「MaaS先進国」として知られています。
フィンランドでは、すでに先述した「レベル3」に該当するサービスも始まっていて、その代表例が「Whim」というアプリです。
フィンランドがMaaS先進国となった背景には、「マイカーへの依存度」があります。公共交通機関の利便性が低く、自動車で移動する人が多いフィンランドでは、首都ヘルシンキなどで交通渋滞が頻発。社会問題となっていました。
そこで、MaaS Global社が政府の支援を受けて開発したのが、世界初のMaaSアプリである「Whim」でした。
「Whim」の特徴
Whimは2016年末に実用化され、複数の交通事業者の情報を統合し、経路検索から予約・決済までのワンストップサービスを実現しました。ヘルシンキ周辺エリアを対象に3通りの料金プランを用意しており、利用者が自由に選ぶことができます。
料金プランのうち、2つは「定額制」となっています。「WhimUnlimited」(月額499ユーロ)に登録すれば、ヘルシンキ市内のバス・電車・地下鉄・トラム(路面電車)の1ヵ月定期券がもらえるほか、タクシーは5kmまで無料、レンタカーやシェアサイクルが使い放題となります。
Whimユーザーの公共交通利用率は63%と、一般ユーザーの48%に比べ大幅にアップしているようです。
まとめ…交通システムの“あたりまえ”が変わるのか
矢野経済研究所は、プラットフォームやアプリなどを含めた日本国内のMaaSの市場規模を、2021年時点で4,905億円9,000万円と推計しています※5。
国土交通省によれば今後、MaaSの市場規模は急成長すると考えられ、2030年には国内市場が約6兆円、2050年までに世界市場が約900兆円にまで拡大するという調査結果もあるとのこと※6。
現在のところ、日本国内の高度なMaaSはテスト段階のものが多いようです。しかし、アプリの普及などにより実用化が進めば、現在の交通システムの“あたりまえ”をパラダイムチェンジさせてしまうかもしれません。
[プロフィール]
野澤 正毅
1967年12月生まれ。東京都出身。専門紙記者、雑誌編集者を経て、現在はビジネスや医療・健康分野を中心に執筆活動を行っている。