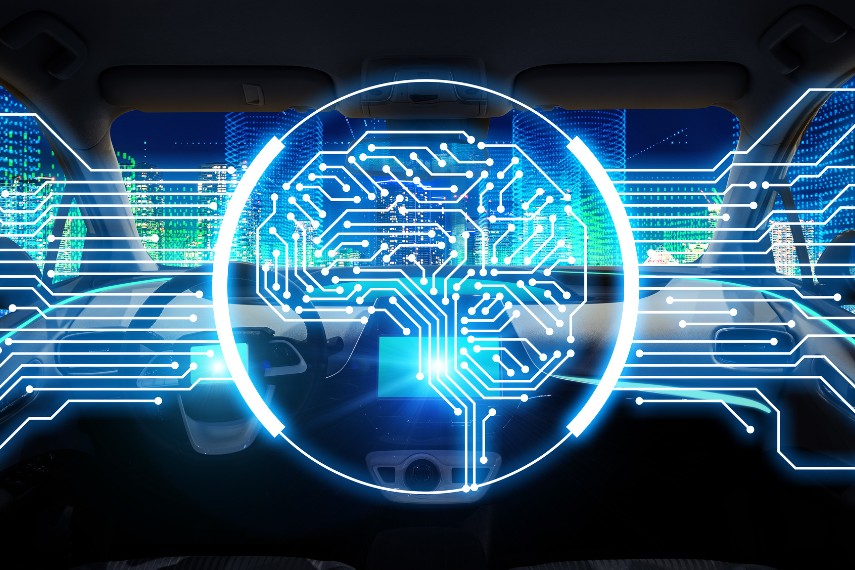念じるだけでメールが送れる?

株式会社アラヤでは、2023年に超高密度脳波計を用いてG-mailを操作することに成功しました。これは取得した発話中の脳波データをAIに学習させ、開発したシステムとAIを組み合わせることで、脳波とChatGPTでG-mailを操作するというもの。
まず「グリーン」や「ピンク」などと発話したときの脳波をAIに学習させます。そして、返信したいメールを選び、そのメールに付けられた色を発話。すると、AIが取得した脳波を解析し、選択したメールにふさわしい数通りの返信内容をChatGPTが提示します。今度は返信の選択肢に付けられた色を発話すると、またAIが脳波を解析して選んだ返信を送信します。
発話時の脳波データを学習していけば、頭の中で「グリーン、グリーン」と念じるだけでもメールや返信の選択が可能です。まだ精度に課題はありますが、将来的にはテレパシーのように、言葉を口に出さずにメールのやり取りができるようになるかもしれません(本研究はJST ムーンショット型研究開発事業の支援により実施)。
また同社は2023年、「空想に輪郭を。」をスローガンにVisionary Labを創設。同年には、脳波が変化するとライトの色が変わる「Colors」というシステムを開発しました。Visionary LabではColorsを使ってババ抜きをおこない、新しい心理戦へと遊びを拡張しています。参加者それぞれに脳波計を装着し、脳波によって色の変わるライトを相手にも見える状態でゲームをおこないました。なにか思考に変化があるとライトの色が変わるため、心理戦が複雑になりゲームが白熱します。
この試みは「人間の知覚に生理反応とコミュニケーションの両方からアプローチし、エンタテイメントにまとめた刺激的なアイデア」と評価され、総務省が主催する2023年度「異能ジェネレーションアワード」で企業特別賞を受賞しました。

画像生成の分野にもブレインテックを活用
量子科学技術研究開発機構(QST)は2023年、画像の線や色、形、質感、概念などの視覚的な特徴を人の脳信号から数値データ化できる「脳信号翻訳機」を構築。人が心に思い浮かべた画像を、ディスプレイ上に再現することに世界で初めて成功しました。翻訳機を作るにはまず、被験者に計1,200枚におよぶ画像を見せて、画像を見ているときの脳波を取得します。同じ画像をAIで数値データ化し、脳信号データとAIの数値データを結びつけることで、脳信号を画像の数値データに変換する翻訳機となるのです。
心に描いた画像を再現するには、この翻訳機を使って被験者が画像を心に思い浮かべたときの脳信号から視覚的特徴を割り出します。その特徴を、生成AIに自然な画像に近づくように描画させます。この技術を応用すれば、病気や怪我などで発話や執筆ができない患者との意思疎通を、頭の中のイメージで行えるようになるのではないでしょうか。
QSTの研究と同じように、脳波から画像を生成するAIが中国の清華大学深セン国際研究生院の研究者によって開発されています。「Dream Diffusion」は、ハイクオリティな画像が作れる画像生成AI「Stable Diffusion」の技術を応用して作られました。従来の画像生成AIは「テキストから画像へ」「画像から画像へ」といった手法が主流でしたが、Dream Diffusionは「思考から画像へ」を目指しています。
これまでも医療などに使うMRIを応用して、fMRI(機能的磁気共鳴画像)信号から視覚情報を再現する取り組みは行われてきました。しかしfMRI装置は持ち運びが難しい場合が多く、専門家が操作する必要などを考えるとコストが高くなってしまいます。一方Dream Diffusionで使用するような脳波を読み取る装置なら、コンパクトに持ち運びができる市販品も登場しているため、より実用的だと期待されています。
とはいえ、脳波から画像を生成するには、脳波を読み取るうえで生じるノイズや限定的な脳波データによる個人差の有無などまだ課題があります。Dream Diffusionは脳波と画像をペアにしたデータに加えて、大量の脳波データから脳波の表現を学習したEEGエンコーダー(脳波符号化器)の仕組みを活用。さらに、画像生成AI、Stable Diffusionを組み合わせて課題の克服を図っています。現在の画像生成精度は45.8%ですが、将来的には神経科学やコンピュータービジョンなどへの応用も見込まれています。
健常者と障がい者が共に競い合える未来を作るブレインテック
BMI(ブレイン・マシン・インターフェース)の研究に取り組む慶應義塾大学理工学部・牛場潤一教授率いる研究チームは、2022年に公開実証実験イベント「BMIブレインピック」を開催しました。
同研究チームが開発したヘッドホン型脳波計「PLUG(プラグ)」を装着し、オンラインゲーム「Fortnite」のキャラクター操作に挑戦する当イベント。装着した脳波計で体の動きを想像した際のシグナルをキャッチし、AIが「足を動かす」「手を動かす」などの動きをキャラクターへコマンド送信します。方向転換はプレイヤー自身が体を傾けることででき、脳からのシグナルと合わせてキャラクターをコントロールできます。
イベントでは当日参加の中高生に加えて、事前に操作のトレーニングを積んだ障がい当事者の選手が参加し、タイムトライアルを行いました。決勝戦では筋ジストロフィーを患う選手が惜しくも高校生に負けてしまいましたが、健常者や障がい者にかかわらず競い合う姿が見られました。今後、ゲームだけでなくパソコンやスマート家電を念じるだけで操作できるようになれば、障がいがあってもより自立した生活が送れるようになるかもしれません。

また、2023年にはApple社が同社のイヤホンAirPods型の機器に、脳波計測機能をもたせる内容の特許を取得。具体的にどのように製品化されるかはまだ不明ですが、Apple社が脳波を活用したアプリケーションをリリースする可能性があるとして、注目を集めています。
医療やヘルスケア、エンタテイメントの進化を加速させることが期待されているブレインテック。しかし、実用化に向けてはまだまだ課題があるのも事実です。まずは脳が厚い頭蓋骨に覆われていることによる、データ精度の問題。そして個人の脳波を活用するということは、「人の頭の中を直接覗く」ことにも繋がります。そのため、プライバシーの侵害や個人情報の漏洩にも十分に配慮する必要があるでしょう。
精度の面では、現在AIを組み合わせることで改善を図る研究が進んでいます。加速するブレインテックの研究は、既存の価値観とはまったく異なる新しい未来を私たちにもたらすかもしれません。
吉田康介(フリーライター)