なぜヒト型ロボットは開発されつづけるのか?
ヒト型をしたロボットの開発・製品化は、一般的に「難易度が高い」と言われています。たとえば、特定の機能を効率的にこなすロボットの開発を目的とした場合、その機能に最適な形態を研究・デザインし、機能に寄与しないパーツは省くことで、正確性を高めコストは低く抑えることができます。しかし、ヒト型ロボットはヴィジュアルデザインをヒトに近づけなければならないめ、機能は制限されやすく、性能に寄与しないパーツを組み込む必要もあるため、正確性が低くコストが上昇しやすい傾向があるからです。
一方で、ヒト型ロボットは現在も開発されつづけています。製品化にたどり着くことが難しいにもかかわらず、開発が後を絶たないのはなぜでしょうか?製品化にたどり着くのが難しいにもかかわらず、開発が後を絶たないのはなぜでしょうか?
テスラが開発したロボット「Optimus」とは?
たとえば、2022年秋にイーロン・マスク率いる「テスラ」が人型ロボット「Optimus」を発売し、話題を呼びました。これは、「人が行なう作業には人型が適している」という視点から「人型のロボットにより人間が行なう作業を代替する」というコンセプトのもと開発されたロボットです。
コンセプトどおり「Optimus」は人間でいえば関節に当たるデバイスであるアクチュエーターを28個擁しています。人の手の構造を緻密に再現したハンドパーツの指は、第一関節と第二関節をもち11パターンの手の動きが可能です。段ボールのように側面が平たく重量のあるものを持ち運ぶこともできれば、じょうろのように湾曲した細いグリップをつかみ、植物の背の高さや鉢の横幅に合わせて水やりをすることもできます。
人間より手先が不器用なのが課題だった、かつてのロボット
アメリカを代表する大手証券会社「ゴールドマン・サックス」は、2000年にニューヨーク本社に600名在籍していた株トレーダーの職をAIに置換し、2017年には2名ま人員削減されたとの報道がありました。(出典)
当時、「ロボットやAIは膨大なデータを処理する頭脳労働は得意だが、人間のように『手先を起用に動かす』『物質の形状や硬度に合わせて握力をコントロールする』などは苦手である」という見解が少なくありませんでした。これは「AIに奪われない職業」に「看護師」や「介護士」が頻繁に挙がる理由の一つでもあります。「AIが膨大なデータをもとに算出した業務フローに従い、我々人間はAIから指示を受け肉体労働を行う未来が来るのでは」としばしば懸念されていました。
例えば、お菓子の製造ラインにおいては、最後の箱詰めのみ人間が行い、また、ハンバーガーの製造ラインでは、レジや接客、収支や予算などの経理業務はロボットが行い、人間はバンズにハンバーグ(パティ)を挟み、ハンバーガー袋で包んで折りたたむ作業のみを行うなどです。
「Optimus」は人体を忠実に模倣したヒト型を追求することで「手先が不器用」という弱点を克服しました。一方で、重い荷物を持ち上げるにはヒトの形にこだわらない形状が有利という側面もあります。日々多くのコンテナが運ばれる物流ヤードで活躍しているのはご存知のとおりクレーンなどの重機です。人間の腕力以上の力仕事を可能にしたい場合、ヒト型は不利にはたらきます。ですが、「Optimus」はこの課題もクリアしています。
本来ヒト型ロボットは重いものをもつのは苦手!「Optimus」が力もちの秘密

人間が重量のあるものを持ち上げるには膝の屈伸運動が重要です。そのため、ヒト型をしているロボットは「人間と同じ滑らかな膝の屈伸運動を、どれだけ人間以上の強度(耐性)で行うことができるか」が焦点になります。
「Optimus」の膝は、人間の膝の前に付いているお皿のような骨「膝蓋骨(しつがいこつ)」に相当するパーツに、4つの棒状のモーターパーツを組み合わせすことで、人間の膝関節を再現しています。
従来のヒト型ロボットはお皿のパーツの中心にモーターを回して屈伸運動を再現していましたが、この方式では直立しているときと膝を曲げきったときに最も回転数が必要であるという問題点がありました。一連の動作に必要な回転数が定まらず、むらがあると、強度をあげるのが難しいからです。
そこで「Optimus」は回転モーターではなく、伸縮モーターで4つの棒状パーツを動かすことで、一連の動作に必要なエネルギーを一定に保ち、強度をあげることを叶えました。なんと、グランドピアノの重さである500kgのものを繰り返し上げ下げすることが可能です。実際に、テスラ開催の人工知能イベント「テスラAIデー2022」では、グランドピアノをホールドしたバンドを関節パーツが持ち上げるというデモンストレーションが行われました。
大活躍したペッパーくんがヒト型の理由は?

ヒト型ロボット史上、もっとも印象に残っている存在の1つが「Pepper」ではないでしょうか。Pepper(以降、ペッパー)くんは、2014年に世界初の感情認識人型ロボットとして登場しました。ペッパーくんがヒトの形をしていることについて、サービスを提供するソフトバンクロボティクスは「(人間は)本能的に、『心を通わせる存在とともに暮らしたい』」という情緒を求めている」と説明しています。人間が行う動作を再現するためにヒトの形をしている「Optimus」とは対照的な理由です。
ペッパーくんの現在は?
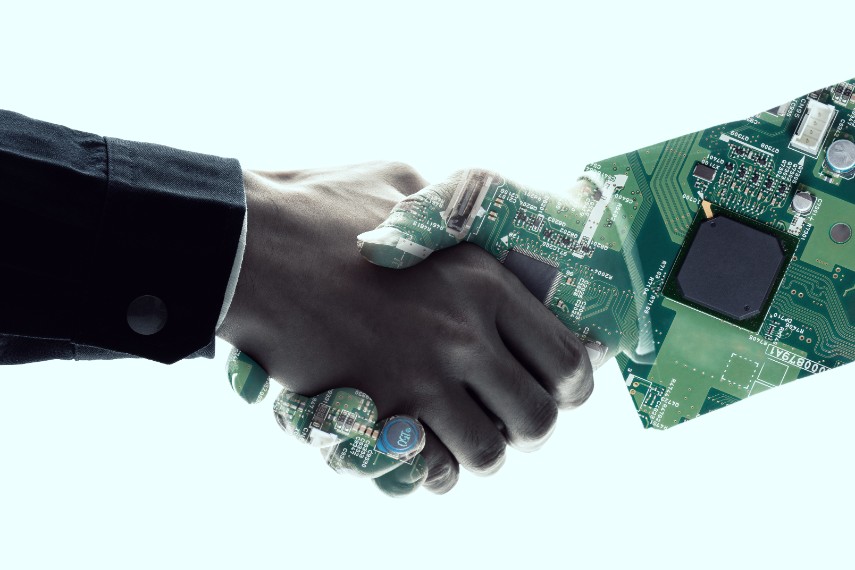
ペッパーくんは2020年夏から製造を停止していますが、保守サービスは継続して提供されています。「生産停止は一時的なものであり、ビジネスの状況を鑑みて生産再開を検討する」と公式に言及されています。ペッパーくんは現在、持ち前のコミュニケーション能力を生かして「集客・接客」「介護」「教育」の分野で力を発揮しています。
ペッパーくんがお出迎えしてくれるカフェ
ペッパーくんの名前を冠しているカフェ「Pepper PARLOR」は、ペッパーくんがレセプショニストとして入り口で出迎えてくれます。入口だけでなく店内でも、各席を回って一緒に遊んだり、お客さんを盛り上げてくれる看板ロボットとして活躍しています。発熱検知を搭載しているので、コロナ禍には感染対策としても力を発揮しました。
ペッパーくんが介護施設でリハビリ指導
介護施設でも活躍しています。介護施設の運営・アプリ開発を手がける株式会社ロゴスが開発した、専用アプリケーションを搭載し、リハビリやレクリエーション指導を行っています。ペッパーくんはヒト型をしているので、シニア層がレクリエーションとして行うゆるやかな体操や運動を、実際にデモンストレーションして見せることができます。音楽をチョイスして胸元のタブレットから流し、親しみのある声で語りかけながらレクチャーしてくれます。
このように、用途に合わせたアプリを開発し搭載することで、ペッパーくんの活躍の場を広げていくことができます。
教育現場でも活躍!子どもたちに学ぶ楽しさを伝えるペッパーくん
子どもたちのプログラミング教育の教材として、全国の小・中・高等学校で活躍しています。子どもたちにプログラミングの楽しさを伝えるには、自身が入力したコードが、「現実世界にどのような変化をもたらすか?」が焦点となります。
ペッパーくんなら、動き、会話、ディスプレイ表示など120種類以上のブロックを組み合わせて自由に設定することができ、親しみやすく、楽しく学ぶことができます。
まとめ
ヒト型ロボットはわたしたちとよく似た形をしていることで、人間を模した動作ができ親しみをもてます。一方で、互いにない特徴・能力も持ち合わせているため、よき友人として補い合うことができます。今後ますますロボットと共存し、助け合っていく未来がくるでしょう。
*
文/福永 奈津美











