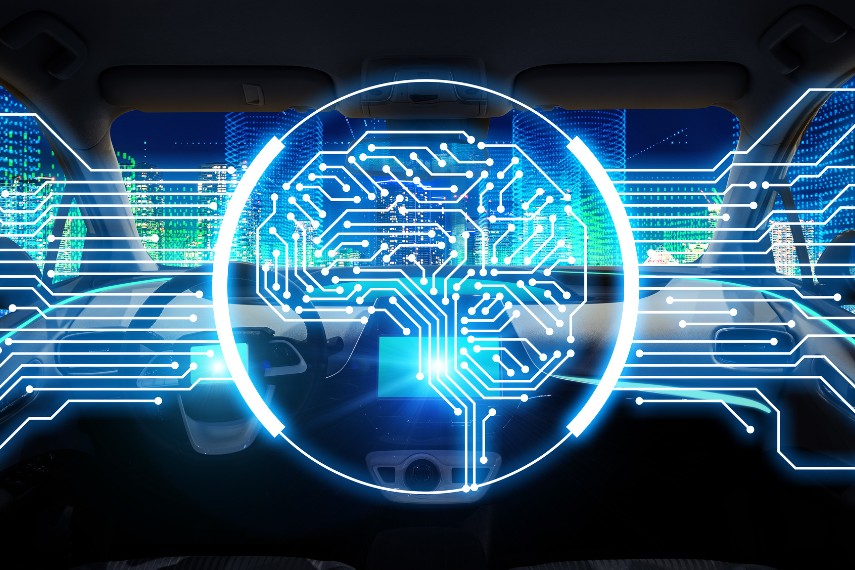ソニー・ホンダモビリティの活動が本格化
今年も1月上旬に米ラスベガスで開催された、世界最大級のITと家電の見本市「CES(コンシューマ・エレクトロニクス・ショー)」に世界の注目が集まりました。
次世代のスマートフォンや健康関連機器などと並んで、CESで最近、存在感を強くアピールしているのが「モビリティ」です。
モビリティとは、乗用のクルマやバイクだけではなく、商用のトラックやバス、さらに歩行や空中を移動することも含めた「次世代の移動手段」の総称です。IT産業の発達によってモビリティの進化も急加速しており、その動向がCESでは肌感覚としてつかむことができます。
今年のCES2023で大きな話題となったのが、ソニー・ホンダモビリティの「AFEELA」 (アフィーラ)です。EV(電気自動車)の新ブランドで、第一弾を2025年からアメリカを皮切りに世界各地で販売の予定だといいます。
テック企業のはしりともいえるソニーと、F1を舞台に日本から世界市場で活躍してきたホンダという、日本を代表する二社がクルマを共同開発することに、大きな時代の変化を実感する人も少なくないでしょう。
そのほか、大手テック企業であるアップルやグーグルは2010年代半ば以降、 CESのみならず自社で開催する開発者向け年次イベントなどで、モビリティビジネスに関する様々な商品やサービスを発表しています。
例えば、スマートフォンとクルマの車載器をつなぐシステムである、アップル「カープレイ」やグーグル「アンドロイドオート」が、すでに日本でも普及している状況です。
では、どうして最近、テック企業とクルマとの関係が目立つようになったのでしょうか?
その背景について、順を追って見ていきましょう。

「クルマは走るコンピュータ」
まずは、クルマの進化について簡単に触れます。
クルマの構造は、車体、エンジン/モーター、サスペンションによる「走る・曲がる・止まる」を基本に設計されています。これは、テック企業がクルマ産業に本格的に入ってくる前でも後でも大きくは変わっていません。
そうしたなかで、80年代からクルマの中に小さなコンピュータを搭載するようになります。一般的にはマイコン(マイクロコントローラー)、またはECU(エレクトロニクス・コントロール・ユニット)と呼ばれ、エンジン、トランスミッション、パワーウインドウなど様々な部品それぞれの動きを電子制御する仕組みです。
それが2000年代以降になると、一般的な乗用車では数十個、高級車では100個近くに及ぶ数のECUが搭載されるようになりました。こうした状況を、メディアが「クルマは走るコンピュータ」と呼ぶようになります。
ユーザーとしては、車内の変化としてダッシュボードのデジタル表示の増加や、カーナビの表示内容がきめ細やかになったことなどに加えて、「まるで、自分の運転が上手くなったようだ」とか「運転での疲れが少なくなったように感じる」といった、電子制御による「走る・曲がる・止まる」の進化を知らず知らずのうちに体感するようになってきました。

「ぶつからないクルマ」の登場
「走る・曲がる・止まる」というクルマの基本に加えて、2000年代中盤頃から「ぶつからない」という観点での機能を持つクルマの普及が進みます。
日本市場で先行したのは、スバル(当時の富士重工業)が90年代に発売した初期的な機能を段階的に進化させた「アイサイト」です。有名タレントが実車で自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)を体験する様子をテレビCMで流し、キャッチコピーにもなっている「ぶつからないクルマ」という発想が世間に一気に広まっていきました。
技術的には、人間の目の原理をもとに、2つのカメラを用いるステレオカメラ方式で収集した画像を、画像認識と呼ばれるコンピュータ技術で解析し、前方車、人、または自転車などとの衝突の危険性がある場合、最初は警報音と表示でドライバーに注意喚起を行い、それでも減速しない場合は自動的にブレーキをかける仕組みです。
アイサイト装着車の販売が一気に伸びたこと、また欧州や日本での自動車アセスメントと呼ばれる安全評価テストの項目に衝突被害軽減ブレーキの高度化が組み込まれたことが影響し、日系メーカー各社は、アクセルとブレーキの踏み間違い防止装置などを含めた、高度運転支援システムの標準装備を進めるようになっていきました。
この分野での技術開発は日系大手部品メーカーの他、海外ベンチャーではイスラエルのモービルアイがひとつのカメラである単眼カメラでの画像認識技術を進化させ、スウェーデンのボルボ、アメリカのゼネラルモーターズ(GM)、また複数の日系メーカーに技術を提供するようになっていきます。

自動運転技術はすでに実用化のステージ
一方で、2000年代中盤以降、アメリカでは国防総省の研究機関が主催した無人カーレースをきっかけに、自動運転の研究開発が幕を開けます。参加者は、スタンフォード大学やカーネギーメロン大学などでシステム工学などを専攻する研究者が主体でした。
この分野に目を付けたのが、グーグルなどのテック企業です。レースに参加した多くの研究者が、テック企業や、欧米の自動車部品大手などに高給でヘッドハンティングされ、自動運転の実用化に向けた開発が着々と進み始めていきます。
2010年代前半になると、自動運転技術の量産化に向けた動きが加速しました。その過程で、アメリカ政府が主体となりドイツ政府と連携する形で、自動運転レベルを公表します。ここには、先に紹介した高度運転支援システムを組み込むという考え方となったことで、産業界では自動運転技術は比較的に短期間に商品化できるという見込みがつきました。
それを機に、エヌビディアや、モービルアイを買収したインテルなど半導体メーカーが自動運転の分野に本格参入し、また中国では自国技術によって自動運転の開発が始まっていきます。
こうして自動運転技術の量産化に関する競争がグローバルで激しくなったことで、日本国内で販売されるクルマにも、スバル「アイサイトX」、日産「プロパイロット2.0」、トヨタ「チームメイト/アドバスドドライブ」、そしてホンダ「ホンダセンシングエリート」といった、高度な運転支援装置をユーザーが日常的に使えるようになってきました。

「つながるクルマ」からデータ活用の時代へ
もうひとつ、ユーザーがテック企業とクルマとの連携を実感するのが、通信によるコネクティビティによる「つながるクルマ」でしょう。
前述のように、スマートフォンと車載器が連携することに加えて、クルマ内部のECUのデータをクラウドに送信するシステムが新車で標準装備されるようになってきました。
ユーザーのメリットとしては、例えばクルマに故障の前兆があれば、その情報をユーザーのスマートフォンと販売店に通知し、修理用の部品を事前に確保したうえで修理日程を決めるといったプロセスを実現できています。
また、エンターテインメントの領域では、ユーザーの属性をクラウド上で解析し、クルマのシステムによるお勧めの音楽の提案や、音声認識を使った高度なカーナビシステムなどが実現しています。
ユーザーにとっては、まるで「クルマ全体がスマホになった」かのような感覚かもしれません。
今後2030年代に向けては、「本格的なEVシフト」と「データ活用による新サービスの時代」と言われており、テック企業による様々なモビリティサービスが次々と生まれる可能性が高そうです。

[プロフィール]
桃田 健史
自動車ジャーナリスト、元レーシングドライバー。専門は世界自動車産業。エネルギー、IT、高齢化問題等もカバー。日米を拠点に各国で取材活動を続ける。日本自動車ジャーナリスト協会会員。